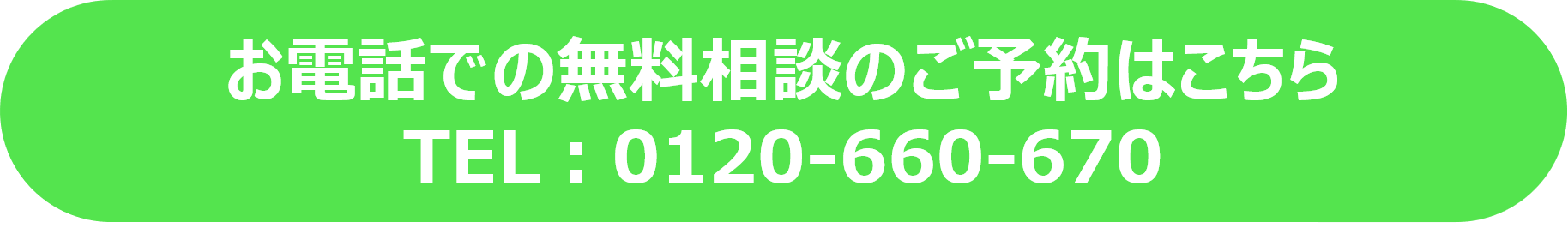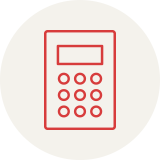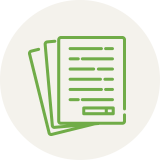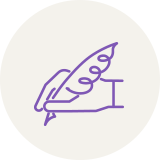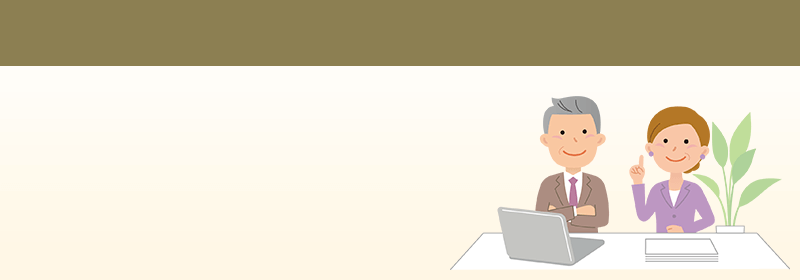目次
はじめに
「成年後見制度」をご存じですか?
この制度は、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援するための身近な仕組みです。
高齢化が進む現代社会において、認知症やその他の理由によりご自身で財産管理や契約を行うことが難しくなるケースが増えています。
また、障害のあるお子さんの将来についてご家族が心配されている場合もあります。
このような時に、「成年後見制度」はご本人やご家族の「安心」を支える制度となります。
成年後見制度には2つの種類があります
成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
それぞれどのような制度か見ていきましょう。
1. 法定後見制度(判断能力が衰えた後に利用)
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所の手続きによって開始されます。
そして、支援を受けるご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
尚、支援を受けるご本人は「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼ばれ、支援する方は「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
2. 任意後見制度(将来の備えとして利用)
一方、任意後見制度とは、判断能力が低下する前に、あらかじめ支援してもらいたい相手と契約(任意後見契約)を交わしておく制度です。
本人が元気なうちに、支援内容や支援者を自分の意思で決められます。
認知症問題が急速に増加する現在、将来に備える安心の仕組みとして、注目が高まっています。
どんなときに利用されているの?
法定後見制度や任意後見制度はどのようなときに利用されているのでしょうか?
以下に、利用例をいくつか紹介します。
法定後見制度の利用例
-
認知症のお父様の財産(不動産や株など)を管理・処分したい。
-
一人暮らしの高齢の親族が、訪問販売などで不必要な契約をしてしまう。
-
認知症の親の通帳や支払いの管理が難しくなった。
-
障害のあるお子様の将来を心配している。
任意後見制度の利用例
-
いわゆる「おひとりさま」のため、将来の入院や認知症に備え、信頼できる人に支援をお願いしておきたい。
-
判断能力がしっかりしているうちに、今後の生活設計をしておきたい。
成年後見制度では、どんな支援が受けられるの?
支援者(後見人等)は、ご本人の意思を尊重しながら、本人に代わってさまざまな法律行為を行います。
主な支援内容についてみてみましょう。
主な支援内容
<財産管理>
-
預貯金の管理、家賃や公共料金の支払い
-
不動産の管理や売買
-
相続や保険手続き
<身上保護>
-
介護・福祉サービス、入退院、施設入所の契約
-
年金、健康保険等の手続き
※ただし、医療同意や本人に代わる婚姻・離婚・遺言の作成、強制的な居住指定、直接の介護などは含まれません。
※居住用の不動産を売却・賃貸する際は、家庭裁判所の許可が必要です。
制度の利用方法
具体的な利用方法は前述のとおりですが、それぞれの制度を利用するにあたってはどのような流れになるのでしょうか?
法定後見制度の手続きの流れ
法定後見制度を利用するにあたっては、以下のような流れになります。
-
☑ 医師の診断書作成、申立書類の準備
-
☑ 家庭裁判所への申立て
-
☑ 調査・審判(鑑定が必要な場合も)
-
☑ 後見人等の選任
-
☑ 東京法務局への登記(登記事項証明書が発行されます)
任意後見制度の手続きの流れ
-
☑ 本人が支援者と任意後見契約(公正証書)を結ぶ
-
☑ 判断能力が低下した時に「任意後見監督人選任」を家庭裁判所に申立て
-
☑ 監督人が選ばれると、任意後見がスタートします。
後見人等にはどんな人がなるの?
-
親族(親・子・兄弟姉妹など)
-
専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士など)
-
市民後見人(研修を受けた地域住民)
-
法人(社会福祉協議会など)
法定後見の場合、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決定します。希望通りになるとは限りません。
一方、任意後見の場合は、事前に任意後見人と契約を締結しているため、本人の希望どおりに後見人が就任することになります。
司法書士ができる成年後見サポート
みたか相続遺言相談プラザでは、成年後見制度の利用を検討されている方に向けて、以下のようなサポートを行っています。
1. 制度のご説明・ご相談対応
成年後見制度の仕組みや違い、どの制度がご家庭に適しているかを、丁寧にご説明いたします。
「後見人って何をするの?」「どんなタイミングで手続きすればいいの?」といった疑問も、お気軽にご相談ください。
2. 家庭裁判所への申立てサポート(法定後見)
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。
当事務所では、申立書類の作成から添付資料の整備、診断書の取得サポート、提出手続きまで一括でサポートします。
3. 任意後見契約の作成支援
将来に備えて任意後見契約を結びたい方には、公証役場での契約に必要な書類作成や内容の検討をサポートします。
必要に応じて、任意後見人候補としてのご相談も承ります。
4. 司法書士が後見人等に就任する場合
ご家族による支援が難しいケースでは、司法書士が第三者後見人として就任することも可能です。
専門職後見人として、中立・公平な立場から、本人の権利と財産を守ります。
成年後見の相談は、地域に根ざした司法書士へ
みたか相続遺言相談プラザでは、三鷹武蔵野エリアや多摩地域を中心に、成年後見制度に関する豊富なご相談実績があります。
高齢の親御さんのサポートを検討している方や、自分自身の将来に備えたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
制度の理解から、具体的な手続き、将来設計まで、司法書士が一貫してお手伝いします。
お問い合わせ・ご相談はこちら
成年後見に関する初回相談は無料です。
相続・遺言・財産管理に関するご相談もあわせて承っております。
三鷹市で成年後見の無料相談実施中
 当事務所では、三鷹市にお住まいの皆様に納得いただき、
当事務所では、三鷹市にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、
三鷹市の方へ成年後見に関する初回無料相談を承っております。
わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-660-670になります。
お気軽にご相談ください。