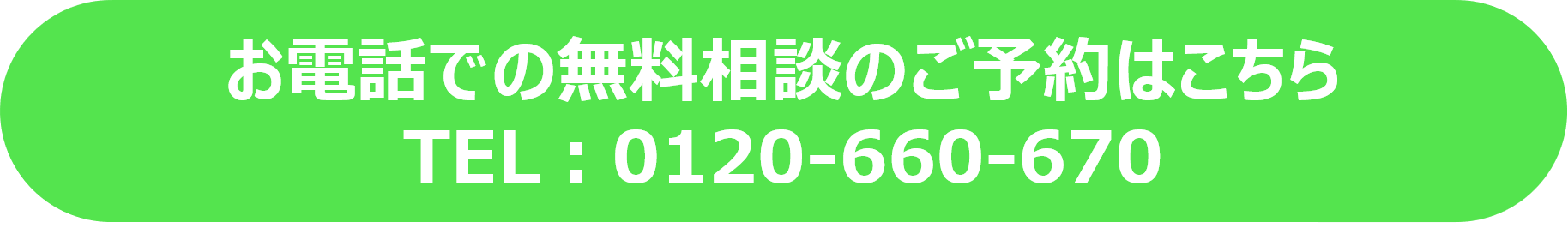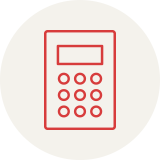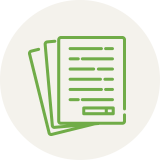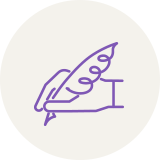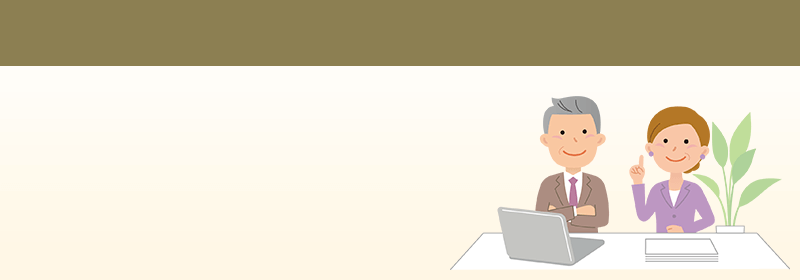「おひとりさま」の財産は誰が相続する?遺言での遺贈や寄付、死因贈与などの選択肢を解説
目次
はじめに
いわゆる「おひとりさま」の相続について、相続人がいない場合の財産は、法律に基づいて誰に渡るかが決まります。遺言による遺贈や寄付、そして死因贈与は、それぞれ異なる目的や方法で財産を他者に承継する手段であり、これらの選択肢をうまく活用することで、「おひとりさま」の意向を反映させることができます。
いわゆる「おひとりさま」の相続とは
2.1 相続人がいないケースとは
いわゆる「おひとりさま」の相続については、相続人がいない場合にどのように財産を承継するかということが問題となります。
相続人がいない場合とは、以下のようなケースです。
・配偶者がいない、またはすでに亡くなっている。
・子供がいない、またはすでに亡くなっている(孫もいない)。
・両親がすでに亡くなっている。
・兄弟姉妹がいない、またはすでに亡くなっている(甥や姪もいない)。
2.2 相続財産清算人の選任
遺言書がなく、相続人がいない場合は、利害関係人等の請求により、家庭裁判所は相続財産清算人を選任することになります。相続財産清算人は、「おひとりさま」の相続財産の管理や負債の清算などを行います。
2.3 相続人がいなければ財産は国庫へ
相続人がおらず、また特別に縁故のあった者(特別縁故者といいます)もいない場合、最終的に「相続人不存在」としてその人の財産は国庫に帰属します。
こうした事態を避けるためにも、遺言書や死因贈与契約などで承継先を指定しておくことが重要です。
遺贈するには遺言が必要
遺贈とは、遺言によって特定の人物や団体に財産を承継させることを言います。通常、特定の金額や財産の一部を遺贈先に承継させる形式で行うことが多いです。遺言書には、遺産を誰に、どのように承継させるかを明確に記載する必要があります。
遺贈を行うための遺言の種類
前述のとおり、遺贈を行うには、遺言書を作成することが必須です。遺言書に誰に承継させるかなどの内容を明記することで、遺言者の意思が法的に効力を持ちます。遺言書には以下の種類があります。
4.1 自筆証書遺言とは
遺言者が自ら手書きで作成する遺言書のことです。法的効力を持たせるためには、以下の要件を守る必要があります。
・遺言書全体を自筆で書く(パソコンなどの機器で作成したものは無効。但し、財産目録を添付する場合を除く)。
・日付と署名を自書し、押印する。
・記載内容が不明確でないようにする(特に承継する財産や相手を明確に記述)。
自筆証書遺言は簡便ですが、法律の要件を満たさないと無効になることがあるため、注意が必要です。
4.2 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人という法律に基づいて任命された専門家によって作成されます。法的効力が非常に強く、公証人によって遺言書の内容に関して不備がないことが確認されます。公正証書遺言を作成する際は、公証役場に出向き、公証人に自分の意思を伝えます。証人も2名必要ですので、事前に準備しておくことが重要です。
4.3 秘密証書遺言とは
自筆証書遺言に近い形式ですが、手書きである必要がなく、パソコンなどで打ち込んだものや印刷したものでも有効です。公証人1名及び証人が2人以上立会う必要があり、遺言者は、自己の遺言書であること並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。そして、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すことによって作成します。
「包括遺贈」と「特定遺贈」とは
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。それぞれ遺言の方式によって以下の特徴があります。
5.1 包括遺贈とは
包括遺贈は、遺産の全部または一定の割合を包括的に指定した受遺者(遺贈を受け取る人)に渡す方法です。具体的には、「全財産をAに」「財産の1/3をBに」といったように、財産の内容を個別具体的に特定せず割合などで記載し遺贈する形式です。遺産全体または一定の割合を指定するため、遺産額が変動した場合、遺贈される財産の金額も変わります。
5.2 特定遺贈とは
特定遺贈は、特定の物品や財産を指定して遺贈する方法です。具体的な財産(例えば、不動産、現金、貴金属など)を個別に指定して、特定の人に遺贈することになります。遺贈する財産の特定が重要で、例えば「私の家をAさんに遺贈する」や「〇〇銀行の預金口座の残高をBさんに遺贈する」といった形です。遺言書で特定された財産は、遺言で指定された遺言執行者によって、遺言に従ってそのまま受遺者に渡されます。
遺言でどちらを選ぶかは、遺産の内容や遺言者の意向により決めていくことになります。
生前に受遺者と契約を結ぶ「死因贈与」
死因贈与は、遺言と似ていますが、法律的には贈与契約の一種です。つまり、贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の間で贈与契約を締結して、贈与者が死亡した場合にその契約内容が発効する仕組みです。死因贈与契約は書面で行い、贈与の内容、受贈者、贈与財産を明確に記載します。遺言書と違って、贈与者と受贈者との間での契約になるため、贈与の内容を直接的に確認できるものとなります。
6.1 遺言と死因贈与の違い
遺言は、一方的な意思表示です。遺言者が自分の死後にどのように財産を処分するかを指定するもので、特定の人(受遺者)に財産を承継するために行います。一方、死因贈与は、贈与者が生前に締結した契約であり、死後に贈与者が指定した財産を受け取ることが決まるものです。これは、契約による贈与であるため、受贈者は贈与契約に同意し、契約に基づいて贈与が行われます。遺言と異なり、受贈者は契約に承諾する必要があります。
特定の団体への寄付
近年、遺贈による寄付先として慈善団体やNPO法人、宗教法人など、社会的に意義のある団体への寄付が増えています。毎年多くの寄付が寄せられており、例えば、「国境なき医師団」(MSF)に対する寄付の数は年間100件にも達することがあります。 寄付を通じて、社会的な活動や支援を行うことができ、特に医療、教育、環境保護などに貢献することが可能です。また、寄付を行った金額が相続税の控除対象になるなど、税制上の優遇措置が受けられる場合があります。
まとめ
「おひとりさま」の相続について、相続人がいない場合、その財産は最終的に国に帰属しますが、遺言書を作成したり、死因贈与契約をしておくことで、特定の人や団体に財産を承継することが可能です。遺言書を通じて自分の意思を伝え、社会貢献をすることもできます。遺言や死因贈与を通じて自分の財産の行き先を自由に決めることができるため、生前にしっかりと検討して作成しておくことが重要です。相続手続きや財産管理について不安がある場合は、司法書士に相談して、適切な対応をとることをおすすめします。
三鷹市で相続・遺言の無料相談実施中
 当事務所では、三鷹市にお住まいの皆様に納得いただき、
当事務所では、三鷹市にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、
三鷹市の方へ相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。
わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-660-670になります。
お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者

- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
-
保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】
- オンライン
相談対応! - 三鷹市外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
みたか相続遺言相談プラザの主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
三鷹市で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで